"私に潜む不安型スタイルの影: 愛着スタイルと心の揺らぎを見つめて"
- Locus of Life
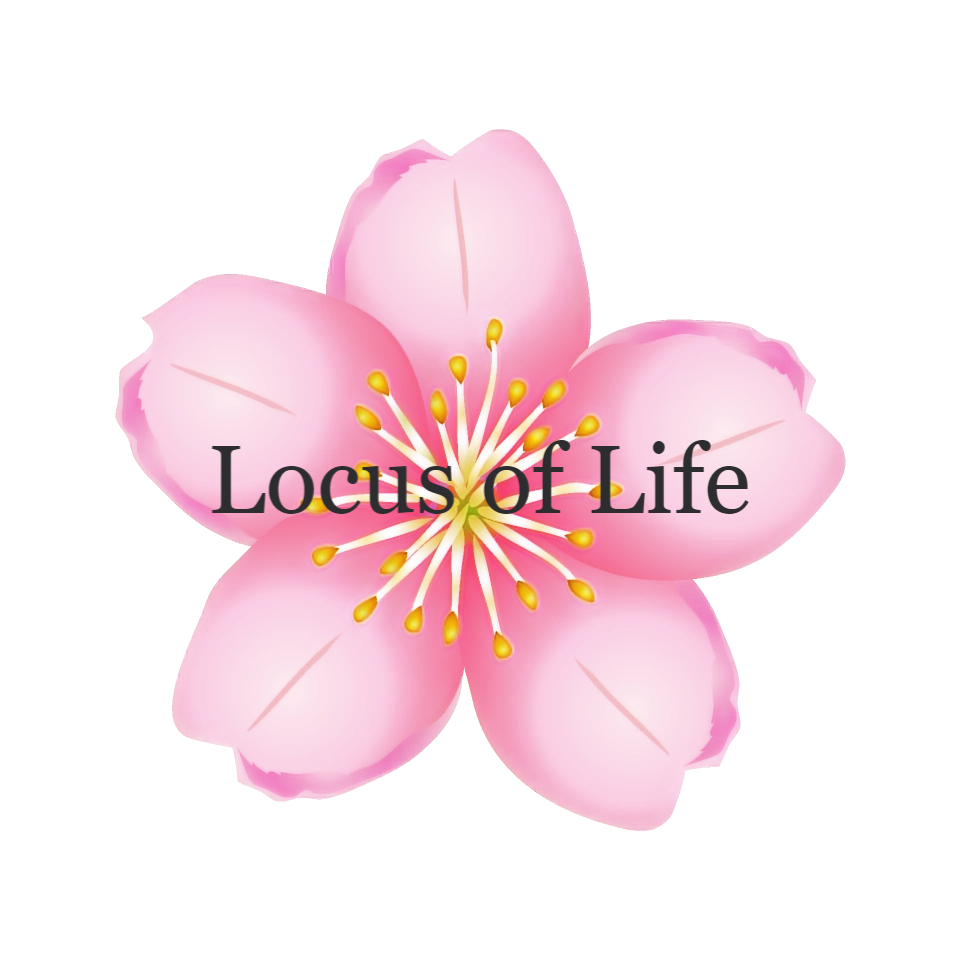
- Jun 13
- 5 min read
Updated: Sep 7
人生の基盤となる愛着(アタッチメント)
私たちが人生で築く人間関係の基盤には、「愛着(アタッチメント)」が深く関わっています。愛着理論は、イギリスの精神分析医ジョン・ボウルビィ(John Bowlby)によって提唱され、人間が生まれながらにして特定の養育者との絆を求めることを示した理論です。特に幼少期の愛着の形成は、その後の人間関係や心理的な安定に大きな影響を与えるとされています。
不安型愛着スタイルとは?その定義と特徴
不安型(Anxious Attachment)は、主に幼少期に養育者からの反応が一貫していなかった場合に形成される傾向があります。子どもは、「愛されているかどうか分からない」「必要な時に助けてもらえるかわからない」といった不確かさを日常的に感じながら育つため、安心感が持てず、常に人との距離や反応に過敏になります。
このスタイルを持つ人は、大人になってからも人間関係で強い不安を感じやすく、相手の気持ちを確かめたくて試すような行動をとったり、相手に依存しすぎたりする傾向があります。「自分は愛される価値がないのではないか」といった自己否定的な思いを抱きやすく、相手のちょっとした態度の変化に一喜一憂してしまうのも特徴の一つです。
愛着スタイルは幼少期だけで決まらない
私自身、自分の愛着スタイルをインターネットでいくつかのテストを通して調べてみたところ、何度やっても「安定型」という結果が出ました。しかし実際の経験を振り返ると、特に恋愛関係や育児の中で、「不安型」の傾向が自分の中にあることを感じる場面がありました。つまり、愛着スタイルは幼少期の両親との関係だけで決まるものではなく、その後の環境や心理状態によっても揺れ動くものなのではないか――そんなふうに私は感じています。
私の幼少期の家族環境
私の父は、日本の昭和時代に典型的だった「仕事一筋」の父親でした。優しい人ではあったものの、朝から晩まで働きづめで、私たち子どもと顔を合わせるのは週末だけ。しかもその週末も、クライアントとの接待や論文の執筆で忙しく、思春期以降、父とゆっくり話した記憶はあまりありません。
たまに休みの日にハイキングや映画に連れて行ってくれることもありましたが、父はとても無口で、会話らしい会話を交わした覚えも少ないのです。今思えば、父なりに私たちとの関わりを大切にしようとしてくれていたのだと理解できますが、幼い私は、常に父がいないことに寂しさを感じていたのだと思います。
一方、母は専業主婦で、いつも家にいてくれました。学校から帰ると私の話をよく聞いてくれていましたが、その反面「勉強しなさい」「部屋を片付けなさい」と繰り返し言われていたこともあり、私は内心で「うるさいなあ」と感じることも多かったです。そんな母との距離感も、安心とプレッシャーが入り混じった複雑なものでした。
このような環境の中で育った私は、「基本的には安定型だけれども、不安型の要素を併せ持つ」という自分の愛着スタイルに納得しています。
日本での仕事とイギリスへの転居
日本にいた頃も、私は客室乗務員として働いていましたが、結婚後はイギリスに転居し、そのまま現地の路線を担当する形で引き続き客室乗務員としての仕事を続けていました。客室乗務員として働いていたころは、外の世界とつながっていられたし、日本にも頻繁に帰ることができていたので、まだ自分を保てていたと思います。
育児と不安の増大
ところが、息子の誕生を機に仕事を辞め、育児に専念するようになると、自分の中の「不安型」の傾向が強く現れるようになりました。英語が思うように話せないこと、イギリスでの生活についてまだまだわからないことが多く、元夫に頼り切っていたこと、友達がいないこと…。気づかないうちに、自分には価値がないと思い込んでしまっていたのかもしれません。
仕事をしていた頃は、社会とのつながりがあり、日本とも頻繁に行き来できたことで、自己肯定感を何とか保てていました。でも、仕事を辞め、初めての育児に向き合いながら、元主人との教育観の違いに悩まされる毎日の中で、私はどんどん不安になっていきました。四六時中息子と2人きりで過ごす日々、大人との会話が恋しくなっても、英語で話すことへの面倒さや自信のなさから、それも避けてしまい、ますます孤立していった気がします。そんな中である日、先に私と息子だけで日本に一時帰国し、後から合流する元主人を空港に迎えに行った時、「君はイギリスにいた時とまるで別人みたいだね」と言われたのを、私は今でもはっきりと覚えています。それほどまでに、孤独の中で息子を育てていた日々は、私の心に重くのしかかっていたのだと思います。
愛着スタイルは変わる可能性がある
「愛着スタイルは変えられる」とよく言われます。確かに、信頼できる人との関係や、自己理解を深める過程の中で、自分の中にある「不安」や「傷つきやすさ」に気づき、それを受け入れていくことで、少しずつ変化していくことは可能だと、私自身も感じています。
こうした変化は、単にスタイルが「別の型になる」というよりも、愛着にまつわる生きづらさや反応パターンに気づき、それに振り回されずに向き合っていけるようになる、つまり「克服していく」というプロセスでもあります。
また、愛着スタイルは固定されたものではなく、人生の中で揺れ動くこともあります。私自身、もともとは安定型だと感じていたにもかかわらず、環境や人間関係の影響によって、不安型の傾向が強まった時期がありました。このように、愛着スタイルは常に変化しうるものであり、今の自分の状態を理解し、その上でどう向き合っていくかが大切なのだと思います。
これから、一緒に考えていきませんか?
このブログでは、愛着スタイルについて一つずつ掘り下げ、自分の経験や思いを交えながら、「どう向き合い、どう変わっていけるか」を探っていきたいと思います。
今回書いた「不安型」についても、まだ語り尽くせないことがたくさんありますが、それはまた次の機会に。これからも一緒に愛着スタイルについて深めていきましょう。



Comments